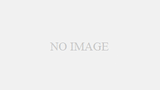6月17日の報道によると大手出版社の「小学館」と「光文社」が、この法律違反で、公正取引委員会から再発防止等を求める勧告を受けたということです。
■ フリーランス保護法とは?
まず簡単にフリーランス保護法のポイントを振り返っておきましょう。
『特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律』
主な内容:
-
業務委託契約時に、契約内容を書面(または電磁的方法)で明示する義務
-
報酬の支払いを60日以内に行う義務
-
不当な一方的変更、納品後のやり直し要求などの禁止
-
ハラスメントや優越的地位の濫用を防止する措置義務
つまり、会社側が「フリーランスだから何してもいい」という態度で接することは、明確に法律違反になり得るのです。
■ 小学館・光文社に何があったのか?
▼ 小学館の場合
-
業務委託契約書の提示がなく、メールベースで発注だけを行う
-
納品後の報酬支払いが数ヶ月遅れるケースがある
-
修正依頼が複数回にわたって追加されるが、追加報酬なし
▼ 光文社の場合
-
初稿納品後に突然キャンセル扱いになる
-
編集者からの強いプレッシャーによる精神的負荷(パワハラ的対応)
-
報酬額の変更が一方的に行われたケースも?
■ フリーランスとしてできる対策
出版社や大手企業と仕事をする際にも、以下の点に気をつけることが重要です。
-
必ず契約書や発注書をもらう(なければ、行政書士に依頼して作成してもらう)
-
修正・追加作業についても都度確認し、メールなど記録を残す(行政書士も一緒に確認)
-
支払いが遅れた場合は督促し、場合によっては労働局等に相談
-
ハラスメントの証拠は可能な限り残しておく
また、業界全体としては、声を上げにくいフリーランスを守るためにも、業界団体や労組的なネットワークの存在が今後ますます重要になるでしょう。
■ 最後に:企業の責任と、我々の声
小学館や光文社といった大手出版社が、仮にフリーランス保護法を軽視していたとしたら、それは非常に重大な問題です。文化や情報を発信する立場にあるメディア企業だからこそ、労働環境にも倫理的責任が問われるべきです。
フリーランス保護法はまだ施行から間もない法律ですが、その実効性は、私たち一人ひとりが「おかしい」と思ったことを可視化し、共有することで育っていきます。泣き寝入りせず、必要であれば我々行政書士に相談する勇気を持ちましょう。