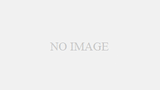アサヒグループHDがサイバー攻撃を受け、多大な損失が見込まれます。
この件から、対策について考えてみましょう。
🧭 BCPの一環として考える「デジタル避難訓練」
― サイバー攻撃に“強い企業”になるための新常識 ―
自然災害や感染症だけでなく、サイバー攻撃も事業継続を脅かす重大リスクになっています。
システム停止や情報漏えい、業務メールの乗っ取りによる信用失墜……。
これらはもはや「ITの問題」ではなく、経営リスクそのものです。
そこで近年注目されているのが、
**「デジタル避難訓練」**をBCP(事業継続計画)の一環として実施する取り組みです。
🧠 サイバー攻撃も“非常事態”のひとつ
BCPは、災害や事故などで事業が中断した際に、
「どうすれば早期に復旧し、被害を最小限に抑えられるか」を定めた計画です。
この考え方をサイバー攻撃にも当てはめると、
“デジタル災害”に備えるBCPが必要になります。
つまり、
「もし自社の基幹システムが止まったらどうするか?」
「顧客データが暗号化されたら、どの業務を優先的に再開するか?」
こうした判断を事前に訓練しておくことが、デジタル避難訓練の目的です。
🧩 デジタル避難訓練の位置づけ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | サイバー攻撃発生時に、事業を止めず・最小限の損害で対応するための実践訓練 |
| 関連するBCP要素 | リスク分析/復旧体制の整備/代替手段の確保/情報伝達の手順 |
| 対象範囲 | 経営層・システム部門・広報・総務・現場担当など全社員 |
サイバー攻撃は「システム障害」だけでなく、顧客対応・報告・法的義務・ブランド信頼など広範囲に影響します。
そのため、BCP全体の中で横断的に組み込むことが求められます。
⚙️ 訓練のステップ
1️⃣ 想定シナリオを作る
たとえば次のようなケースを設定します:
-
社内サーバーがランサムウェアに感染
-
社員のメールアカウントが乗っ取られ、顧客に不審メールを送信
-
クラウドサービス障害で業務が停止
このように「起こりうる」事態を想定し、対応プロセスを検証します。
2️⃣ 初動対応と報告ルートの確認
CSIRT(インシデント対応チーム)や情報システム部門、経営陣への連絡フローを確認。
同時に、被害拡大を防ぐための初動対応(ネットワーク遮断、ログ取得など)を練習します。
3️⃣ 社内外への情報共有訓練
顧客・取引先・メディアへの公表対応、個人情報保護委員会への報告など、
広報・法務の連携訓練も欠かせません。
4️⃣ 復旧と代替手段の確認
バックアップからの復旧、代替システムへの切替手順を確認。
「業務を止めない仕組み」がBCPの核心です。
5️⃣ 事後レビュー(インシデントレビュー)
訓練の成果と課題を整理し、
-
ルール・マニュアルの更新
-
再発防止策の策定
-
再訓練の計画
を実施します。
🧱 BCPとしてのメリット
-
経営リスクの可視化
実際に訓練を行うことで、どこに弱点があるかを明確にできます。 -
組織横断の危機対応力向上
IT部門だけでなく、経営層・広報・総務が一体となった“全社防御体制”を形成できます。 -
社内意識の醸成
サイバー攻撃を「誰かの問題」ではなく、「全員のリスク」として共有できます。
🌐 まとめ:サイバー攻撃も“BCPで備える時代”
自然災害への備えが当たり前になったように、
これからはサイバー攻撃にもBCPで備えることが企業の常識になります。
「デジタル避難訓練」は、単なるIT訓練ではなく、
経営のレジリエンス(回復力)を高める戦略的施策です。
🔐 サイバー攻撃は防ぎきれなくても、被害は減らせる。
その鍵を握るのが、BCPの中で行う“デジタル避難訓練”です。